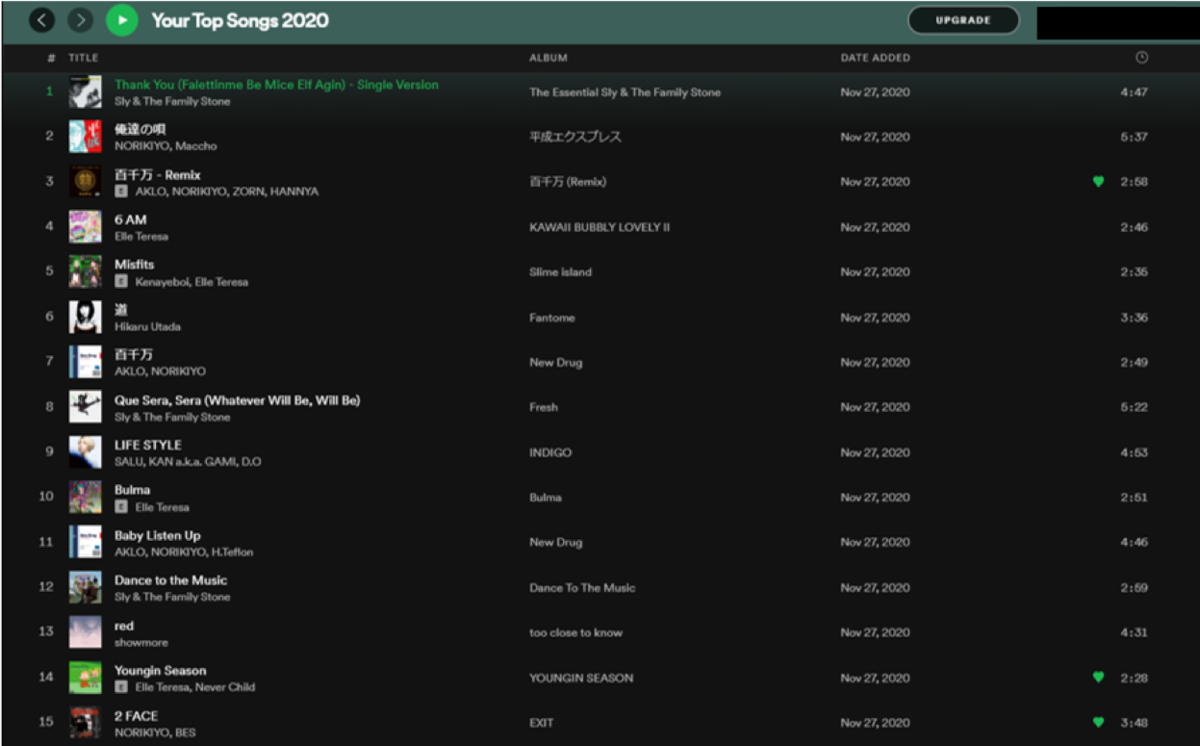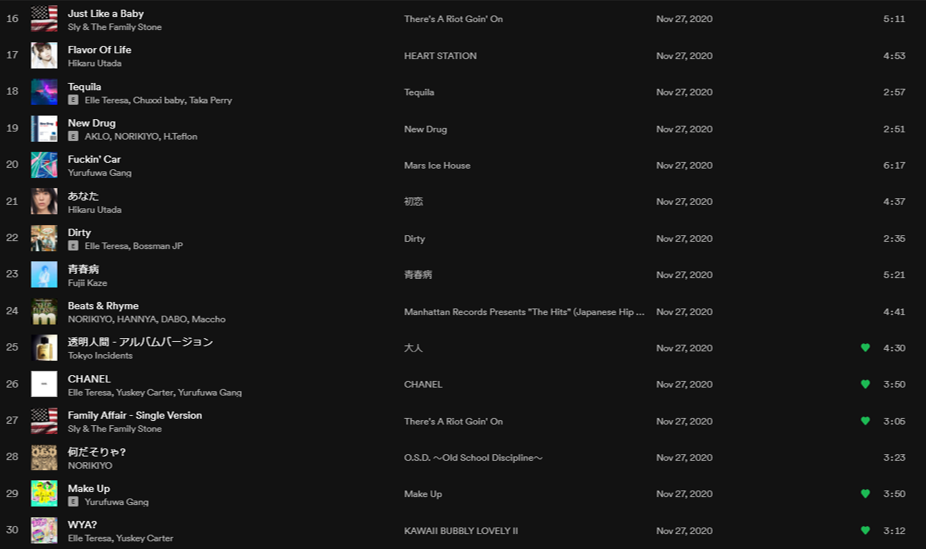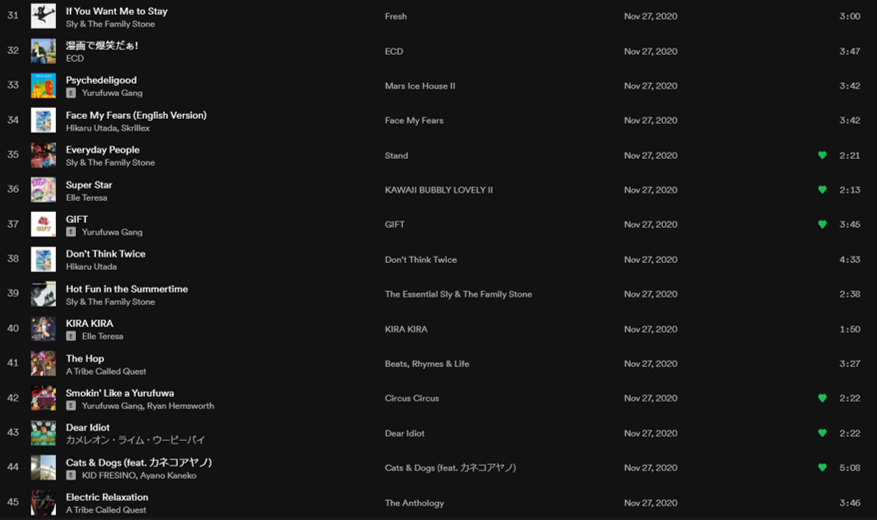Kumar N, Zhao HN, Awoyemi O, Kolodziej EP, Crago J, 2021, Toxicity Testing of Effluent-Dominated Stream Using Predictive Molecular-Level Toxicity Signatures Based on High-Resolution Mass Spectrometry: A Case Study of the Lubbock Canyon Lake System, Environ Sci Technol 55(5): 3070-3080.
河川水や処理排水を網羅的に化学分析して、その結果とin vitroのデータベースやトキシコゲノミクスのデータベースと組み合わせることで、生じうる生物学的なハザード(=どういう影響が起きるか)やリスクの大きさを予測しようとする研究があります。例えばToxCastを活用したCorsiら(2019, Sci Tot Environ)など。
しかしそのようなデータベースを活用した手法だと対象にできる化学物質の数が限定されてしまいます。そこで、このKumarら(2021)はSimilarity Ensemble Approach(SEA)という手法を使って、化学物質のターゲットになる生体分子を予測しています。SEAを用いることでToxCastやComparative Toxicogenomics Databaseの4~5倍以上の化学物質を考慮することが出来ています。ターゲット分子を予測した後はPANTHERでGene Ontologyのenrichment解析。
この論文自体は、zebrafishのqPCRで確認はしているものの、正直「やってみたよ」の領域を脱し切れていませんが、SEAという手法を知ることができたのは大きな収穫です。ググったら、SEAは化合物のBLAST版などと紹介されてました。創薬分野で主に使われているみたいです。
Lemieux GA, Keiser MJ, Sassano MF, Laggner C, Mayer F, Bainton RJ, ... Ashrafi K, 2013, In silico molecular comparisons of C. elegans and mammalian pharmacology identify distinct targets that regulate feeding, PLoS Biol 11(11): e1001712.
これは環境分野の論文ではないですが、マウスやヒト以外にSEAの予測を適用している論文ということでチラ見。線虫C. elegansの摂餌行動に影響を及ぼす化学物質をSEAで予測し、実験的に検証しています。面白いのは、SEAで予測するときに、ほ乳類の生体分子をターゲットにしていること。
生態リスク・生態毒性に応用するなら、SEAで検索対象にするターゲットの生体分子をどこまで生物種特異的にするべきか(無脊椎動物への影響予測のためにほ乳類の生体分子を使えるかどうか)が鍵になりそうです。
ということで実際にSEAを使ってみました。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校が運営しているHP(https://sea.bkslab.org/)に行き、興味のある化学物質のSMILESを打ち込むだけ。
SMILESはPubChemから取ってきました。
検索したのは ①ネオニコチノイド農薬の1種であるイミダクロプリド、②幼若ホルモン様作用を示す農薬であるピリプロキシフェン、③有機リン系農薬であるクロルピリホス、④その代謝物であるクロルピリホスオキソン。
まず①イミダクロプリドの結果。

SEAのライブラリに昆虫の生体分子も含まれていたためか、ハエなどのニコチン性アセチルコリン受容体などがヒットしてます。しかしマウスのアセチルコリン受容体もヒットしていますね。昆虫などに選択毒性を示すネオニコチノイドですが、ほ乳類の生体分子情報もターゲット予測に使えそうなことが伺えます。
次に②ピリプロキシフェン。

今度はTanimoto係数が全て0.5未満で、類似度の高い生体分子がヒットしませんでした。うーむ、なぜでしょう。SEAのライブラリが無脊椎動物(というか節足動物)の幼若ホルモンなどを含んでいないのか、それともピリプロキシフェンは代謝物が主に毒性を発現するのか(後述)…?
そして③クロルピリホス。

またもやうまくヒットせず。しかし、クロルピリホスの毒性は主にその代謝物であるオキソン体によって生じるので、クロルピリホスオキソンを代わりに検索してみました。
最後に④クロルピリホスオキソン。

今度はヒットしました。(マウスの)アセチルコリンエステラーゼがヒットしたのも想定通りです。よく分からないのもヒットしてますが、この妥当性は不明。。
以上、ざっと試しに使ってみて生態毒性・生態リスクに使用する際には、
i) ターゲット生体分子にどの生物種の情報を使用するか
ii) 代謝活性化する化学物質の場合の考え方
あたりがポイントになりそうだと思いました。
SEAで検索対象にするライブラリはChEMBLから引っ張ってきているみたいですが、カスタム設定もできるみたい。よく分からなかったので、今回はやってませんが。。。もし任意の生物種のアミノ酸配列だけ用いてSEAや類似の推定が出来れば面白そう。